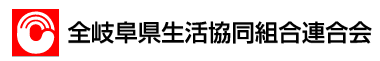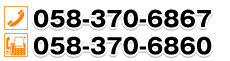2025年4月4日(金)、岐阜県社会福祉協議会(以下、岐阜県社協)、コープぎふ、全岐阜県生協連で「災害支援」をテーマに第4回懇談会を開催しました。岐阜県社協から3名(総務企画部:藤田部長、土岐課長、飯田主事)、コープぎふから2名(市川執行役員、兼子部長)、県連から1名(佐藤専務理事)が参加しました。
この日は、まずそれぞれの災害支援に関わる2024年度活動の特徴的な取り組みや2025年度に向けて検討していること等を紹介しあいました。
全岐阜県生協連からは、6/8「石川県輪島市での炊き出し支援活動」、11/8「岐阜県生協大会での講演会の開催」、11/14-15「拡大県連理事会研修(倉敷市)」、11/19「岐阜県災害ボランティア連絡調整会議設置訓練」、「令和6年能登半島地震及び能登豪雨災害支援募金」等について報告しました。
コープぎふからは、10/31-11/4「能登半島地震及び能登豪雨の被災地支援への職員参加」、10/29「防災セミナー」、1/22「防災時を想定した炊き出し訓練」、2/18「防災企画 心のケア」、3/18「「3.11を忘れない」知って備えに役立てよう」等の様子が報告されました。
岐阜県社協からは、「市町村社協における被災者支援活動の体制整備」課題として実施された、「災害ボランティアセンター担当職員研修」や「能登半島地震における被災地支援を振り返る会」「災害ボランティアセンター運営支援者研修」「能登半島地震における支援の実施(職員派遣やボランティアバスの運行)」等の実施状況が報告されました。さらに、「三者連携による体制整備の促進」計画としては、岐阜県災害ボランティアコーディネーターの設置や体験型研修、災害時専門ボランティア受入研修の開催内容も紹介されました。
その後の意見交流の中では、災害協定を締結している市町村と生協の「顔の見える関係づくり」の進め方や、市町村における三者連携(行政・社協・生協などNPO等)の重要性について意見交換しました。岐阜県社協からは、現時点で県内42市町村のうち8市町が協議体を設置済みで、2市が設置検討中であることが紹介され、担当者がかわっても関係を維持していける取り組みや、さらなる協議会設置の促進が県社協の重要課題として設定されているとのことでした。
また、コープぎふで準備が始まった、生協組合員や職員OBによる災害ボランティア組織づくりの進め方について県社協の方から経験も踏まえて助言をいただき交流しました。土岐課長からは、「ボランティア組織づくりをしましょう」と言っても人は集まるものではなく、「こんなことをやるので、一緒にやってみませんか?」と具体的に呼びかけることが大事であること、ふだんの生活に寄り添う形で「趣味の延長線上」として捉えてもらえるくらい敷居を低くしていくことが大切だと教えていただきました。ボランティア活動は人のためのものではあるけれど、それを通して自分や家族のため、そして地域のためになることだと話されたのか印象に残りました。
また、2025年度もいくつかの対象別の研修企画を予定されているとのこと。ぎふNPOセンターと連携して行われる「災害時専門ボランティア受入研修」は、災害時専門ボランティアの基本的な内容でカリキュラム化されているようなので、これからのボランティア組織づくりに有用だと感じました。
岐阜県においても、2025年度は災害などに強いインフラや医療・防災システムの整備の施策が進められようとしています。各地域で三者連携の取り組みが本格化していくことが予想されており、ぜひ、生協の私たちも市町村行政や市町村社協との関係を整え直して、防災・減災や災害支援の対応力を高めていきたいと思いました。
今年も、新年度早々に懇談の場を設けていただき、貴重なアドバイスをいただくことができました。岐阜県社協の皆さまに感謝いたします。